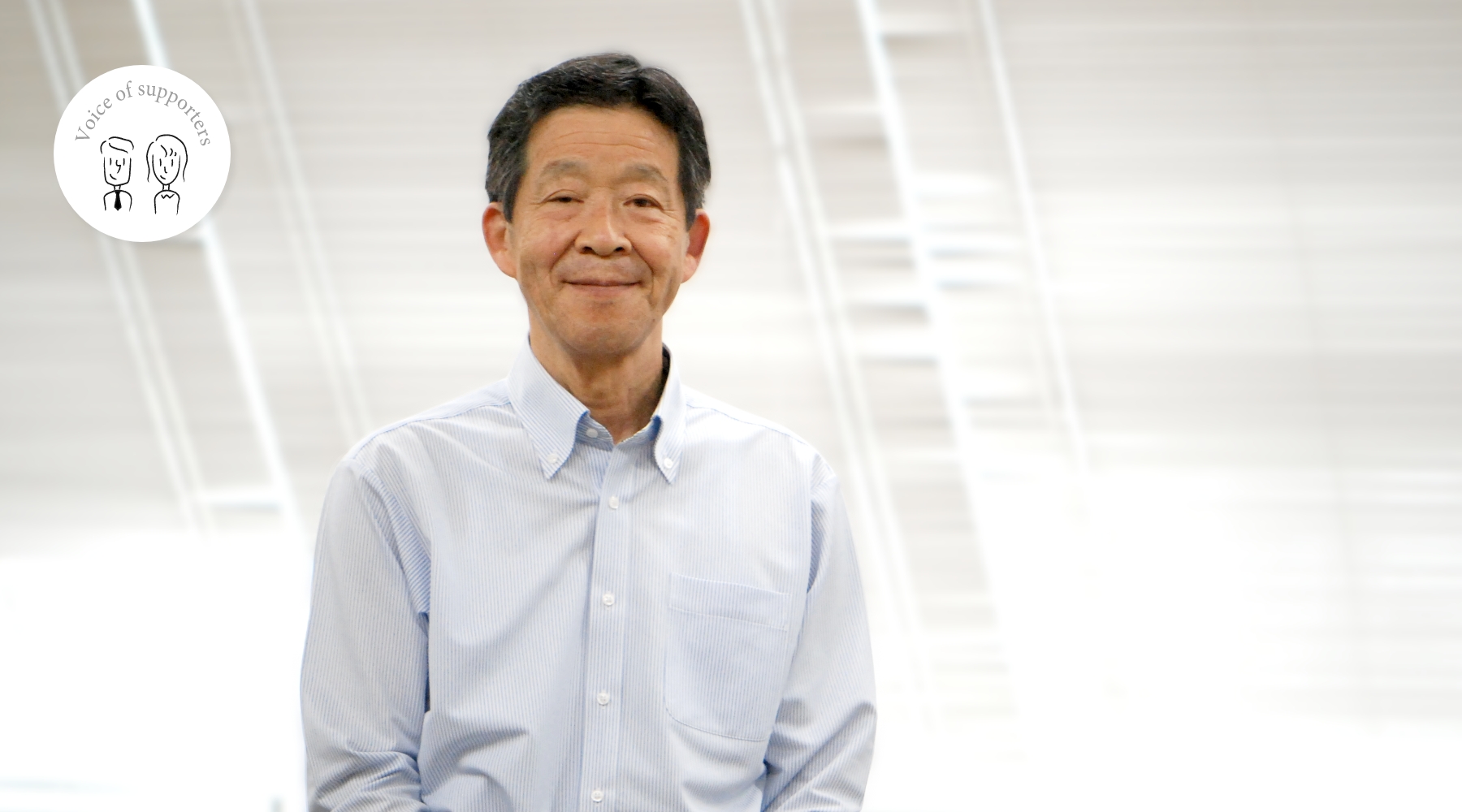
目次
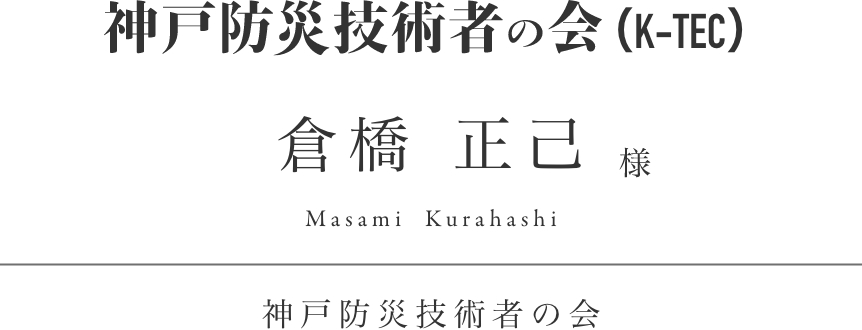
【インタビュー】阪神・淡路大震災に学ぶ。行政任せにしない、災害に備えた地域コミュニティの重要性と世代交代の課題。
1997年1月17日午前5時46分。まだ夜が明けぬ冬の早朝、巨大な揺れが神戸を襲った。明石海峡付近の深さ16kmを震源とする阪神・淡路大震災だ。M7.3の地震は、震源付近の神戸の街を一変させた。
「それは大変な光景でした。あちこちで救出活動が行われていて、救助を待つ人を励ます声がたくさん聞かれました。周辺の学生が救出活動を手伝ってくれて、みんなで救助にあたりましたね」
こう話すのは、神戸防災技術者の会事務局を務める倉橋正己さんだ。当時神戸市の職員だった倉橋さんは、震災時の変わり果てた街の再建を担った人物の一人だ。橋脚が折れ、635mに渡って横倒しとなった阪神高速道路神戸線。埋立地である六甲アイランドやポートアイランドでは液状化現象による地盤沈下。さらに神戸市中心街の三宮では、折れ曲がった大型ビルが道路を塞ぐなど、神戸の被害は甚大だった。
「オフィス街やインフラの被害も大きかったですが、木造家屋の密集地の被害はとくに深刻でした。ほとんどの木造家屋が倒壊した地域もありました」
地震によって、神戸市を中心に10数万もの家屋が一瞬にして倒壊した。地震発生が早朝だったことから就寝中の人が多く、倒壊した家や家具の下敷きとなってたくさんの人が犠牲になった。阪神・淡路大震災から28年が経った現在でも、かつてない都市圏での災害として大きな教訓になっている。

震災を風化させてはならない。次世代へ伝えたい教訓。
「神戸防災技術者の会では、その教訓を次の世代へ伝承する活動をしています。会員には当時市の職員だった人や現役の人もいますよ」
発足のきっかけは『震災の風化』だったという倉橋さん。阪神・淡路大震災から10年が経ったころ、震災当時の神戸市長が、震災の記憶が薄れ始めてきたことを危惧して、後世の人にも伝えていかなければならない教訓だと立ち上げを指示されたことによる。
「市の職員は若い人も増えていますので、当時のことを知らない世代に、地震があったときにどうやって街を守るのか、どういう行動が求められるのかを研修しています。要望があれば、ほかの自治体の職員の人へも防災の研修をしていますよ」
教訓の伝承は自治体の職員のみならず、大学などでの講義も行われているという。ほかにも地方からの修学旅行生向けに、防災学習として震災から学んだ多くのことを伝えているそうだ。また神戸防災技術者の会では、災害発生地域への支援も行っている。
「国内外問わず支援活動をしています。以前台湾で大きな地震がありましたが、私たちの会員が派遣されて現地で活動していました。ほかにも東日本大震災の被害にあった地域とは何度も交流をさせていただいています」
支援の輪に国境はない。災害を経験し、多くの支援を持って復興を遂げた街だからこそ、神戸はその痛みと支えあいの大切さを理解しているのだ。

行政も住民も、本気で街のことを考えたからできた復興と再建。
震災後は復興に向けて長い道のりを歩むことになる。なかでも被災者の住宅や生活再建は優先度が高い。しかし、神戸市が新たなまちづくりを計画した六甲道駅南地区の再開発事業は、多くの難題が待ち構えていた。
「10階建てのビルが震災で傾いてしまっていて、周囲を再開発するためには取り壊す必要がありました。しかし取り壊しには、ビルの所有者全員の合意がないと進められません」
早い対応が求められる状況にあっても、大きなビルは所有者の数が多く、連絡が取れなかったり、住宅や区画に被害がない人は再開発に否定的だったり。交渉は難航した。
「神戸市は、再開発にあたって1ヘクタールの大きな防災公園を地区の真ん中に配置し、公園を取り囲むように900世帯が入居できる巨大な複合マンションの建設を計画したんです。しかしこれが住民から猛反対されたんですよ」
住民の意見はさまざまだ。「情緒豊かな下町が変わってしまう」、「自分の土地がここだと言えなくなる」、「うちは建物が残ったからそもそも再開発には反対」などといった、それぞれの事情や思い入れを抱えたものだった。神戸市が災害に強い街をつくるために用意した再開発計画であったが、それならと住民たちも「こういう街に住みたい」と自身で考えをまとめて市に提案した。
「住民の有志が50人集まり、神戸大学の先生にも入ってもらって、大きな公園は要らないから小さい公園を各ブロックに分散配置して、低層や中層マンションも作って欲しいとか、せせらぎのある遊歩道を作って欲しいとか、たくさんの要望が出てきましたね」
計画の協議を進めたい神戸市と、生活再建の見込みを立てるために土地の評価額や再開発ビルの床価格の協議を先に進めたい役員とで、議論は堂々巡り。再開発事業をしたくないという役員の声も強く、なかなか決まらない計画に苛立ちを募らせ、会議は毎回行政批判が続いたという。
「仮設住宅で暮らしている人たちは、早く計画を決めて進めたいんです。一方、住宅が無事だった人たちはできれば再開発事業をしたくないという意見が多かったんですが、やはり地域の知り合いですからね、地区内の仮設住宅で暮らす住民のことを想って、みんなで協力して事業に取り組むことになったんです。」
行政任せにせず、住民たちが知恵を絞って納得がいくまで十分議論し、本気で再開発を考えたことで街に対する愛着がより深まった。そして、こうした街や人を想う気持ちが、神戸が災害に強い街になるための基盤になったと言っても過言ではないだろう。

行政任せにしない。地域コミュニティがもたらす粒度の高い災害対策と支えあい。
前述の初期計画にもあった1ヘクタールの公園は0.93haと少し縮小されたものの、広い公園が採用された。春はシートを敷いて花見を愉しんだり、夏になればラジオ体操をしたり、冬には餅つき大会が開催されたりと、地域の交流の場としても活用している。
「当初はそんな大きい公園はいらないと言う住民も多かったんですが、結果的に大きい公園にしたことでいろんな用途に活用することができたんです。灘区のだんじり祭りは最初の集合がこの公園で、ここからパレードが始まるんですよ」
何気ない日常や催しによる交流の場が、再開発によって生まれた。暮らしを通して地域のコミュニティを形成できるのは、防災にも大いに役立つと倉橋さんは話す。
「市内では、震災が起きてからすぐにまちづくり協議会ができた地区もありました。安否確認や配給の仕分けを行政任せにせず、地域コミュニティが市と連携して積極的に活動していました」
ほかにも避難所生活を続ける住民を1日でも早く自宅に戻れるよう、大工を呼んで壊れた住宅を修繕するなど、地域の輪を駆使して生活再建を図っていたという。しかし、積極的なコミュニティ活動を継続させることは容易ではないと倉橋さんは続ける。
「地域コミュニティが機能している地区には、みんなを引っ張ってくれるリーダーがいるんです。活動が薄れてしまったコミュニティは、世代が入れ替わったり、次のリーダーが育たなかったり」
こうした世代交代の課題は、緊急時では重要な問題にもつながりかねない。倉橋さんによれば、避難所運営は行政の職員だけでは地域住民も言いたい放題になってしまい、混乱状態になることもあるのだとか。また平時での防災活動も行政任せにしないことが重要だと話す。
「行政がすべての地域の細かい部分まで把握しているケースは少ないですから、災害時には地域住民同士によるコミュニケーションや情報交換が大切なんです」

行政が用意する防災ツールはいくつかある。たとえばハザードマップもそのひとつだ。しかしそのハザードマップを見ただけでは防災活動とは言い難い。それを使ってどう避難するのかを、地域で話し合う必要があるという。
「避難ルートが塞がれてしまった場合に備えて回避ルートも考えなければなりません。確保が難しければ行政に相談する必要がありますし、足の悪い高齢者等が住んでいる場合は、誰が避難のサポートをするかなど、地域コミュニティで考えることは多いんです」
震災を知る人と、知らない人への世代交代は避けられない。また、行政ばかりに頼ってもいられない。発生が確実視されている南海トラフ大地震をはじめとする、あらゆる災害による被害を、最小限に抑えるためにできることは何か。地域コミュニティでできる備えは何か。自分ごととして考えなければならないときが来ているのだ。